目次
SNSマーケティングで使えるSNS媒体の攻略法
スマホやパソコンを持ってる方なら、
今や実生活で一日一度は必ずと言っていいほど
目にしているであろうSNS。
ビジネスにおいてもこのSNSの存在は、
今や欠かせないものとなっています。
特に、SNSを使ったマーケティング
『SNSマーケティング』は今や欠かせない
マーケティング手法となっています。
個人でも企業でも誰でも使えるからこそ、
利用するSNSの攻略法について知っておかなければ
ライバルと差をつけて稼ぐことはできません。
今回は主要SNS5つについて、
・Facebook
・Instagram
・X(旧Twitter)
・TikTok
・LINE
それぞれ媒体のアルゴリズム(※1)やより優先表示されるポイント
についてそれぞれ解説していきます。
・これからSNSマーケティングを始めていきたい
・すでにやってるけどうまく宣伝できてない
そんな方にこそ知ってほしい攻略法になりますので、
ぜひ最後まで読んで運用に活かしてください。
※1:アルゴリズムとは?
問題解決の手順やルールのことです。
SNSではユーザーの行動データに基づき、
どのようにコンテンツを配信するか決定するルールを指します。
1:Facebook
Facebookは実名登録が基本のSNS媒体です。
旧知の中の友人や、
一度は実際に会ったことがあるユーザー同士
での交流がメインとなっています。
利用者の割合を見てみると、
30~40代の男性の利用割合が多い特徴があります。
ビジネスシーンでの交流や、
リアルな繋がりといった特徴から
よりフォーマルなシーンでの利用も目立ちます。
また、最近のビジネスシーンでは
名刺代わりに使われることも多く、
商品やサービスのPRに使われたりします。
他にも、Instagramとも連携可能で
Facebookで投稿した内容を
Instagramにも同時投稿することができます。
Facebookのアルゴリズムとは?
Facebook上で、
『おすすめ』としてユーザーに表示されるため、
理解しておいて欲しいアルゴリズムは以下になります。
| ①:インベントリー | 友達やフォローしているページがシェアした一連の投稿のことです。 『ニュースフィード』や『Watch』といった場所によって、 表示される投稿の種類が異なってきます。 (Facebook内の『ニュースフィード』には、ユーザーに繋がっている相手がシェアしたコンテンツが表示されます。) |
| ②:シグナル | 『誰が投稿したのか』『いつ投稿されたか』といった何十万ものシグナルが考慮されます。 |
| ③:予測 | 『ストーリーにコメントする可能性はどのくらいか』 『時間を費やしてそのストーリーを読む可能性はどのくらいか』 『動画を最後まで見るか』 『ストーリーが参考になったと言う可能性はどのくらいか』 Facebookのアルゴリズムによって、ユーザーがその投稿に反応する可能性がどれくらいか上記に挙げるような予想を実施します。 |
| ④:スコア | 2で挙げたシグナルを統合したものを使い、関連度スコアを作成します。 関連度スコアとは、その投稿に利用者がどのくらい関心を持つのか、 Facebookが推定する数字のことです。 それを元に 『クリックする可能性』 『この投稿に時間を費やす可能性』 『いいね!、コメント、シェアをする可能性』 『この投稿が参考になると思う可能性』 『この投稿がクリックベイトである可能性』 『この投稿が低品質なウェブページにリンクされている可能性』 上記のような予測を立てて、利用者がその記事をどの程度参考になると思うかについてのFacebookの最善の予測である関連度スコアに反映されていきます。 |
細かく書いていますが、
Facebookのアルゴリズムを重視した投稿をする場合、
自社アカウントをフォロー・シェアしてもらうことが重要です。
また、Facebookの場合、
ユーザーにとって参考になるような情報を
いかに提供できてる投稿なのかが評価を左右します。
2:Instagram
Instagramの特徴として、
写真や動画を用いて投稿します。
そのため、ビジュアルがより重視され、
グルメやファッション、化粧品などの
PRに使われることが多いです。
写真や動画をただ単に投稿するのではなく、
『いいね』や『共有したくなる』ような
工夫をすることが重要です。
また、ブランディングが目的の場合、
投稿のレイアウトに統一感を出すことが大切です。
Instagramの仕様上、
投稿にURLを載せてもクリックができません。
そのため、公式サイトなどに誘導したい場合、
自社アカウントのプロフィールページを
開いてもらう必要があるので、そこも工夫が必要です。
Instagramのアルゴリズムとは?
次にInstagramのアルゴリズムを見ます。
便宜上、フィードと発見タブに分けて解説していきます。
・フィード
| ①:利用者のアクティビティ | ユーザーが過去に『いいね』『シェア』『保存』『コメント』といったアクションした投稿を基に、そのユーザーが興味を持ちそうなコンテンツを判断して表示します。 |
| ②:投稿に関する情報 | その投稿に対して『いいね』『シェア』『保存』『コメント』をどれくらいの人が行ったか、そしてそれらのアクションがどれだけ早く実行されたかといったシグナルを見て、投稿の人気度を分析します。 |
| ③:投稿者に関する情報 | その投稿者に対し、ユーザーがどれくらい興味を抱く可能性があるかを把握するための項目です。 直近数週間で、その投稿者がほかの利用者と何回やり取りしたかといったシグナルが含まれます。 |
| ④:特定のユーザーとのやり取りの履歴 | ある特定のユーザーの投稿を見ることに、どのくらい興味があるかを把握するためのシグナルになります。互いの投稿にコメントをしているかどうかなどのアクションが含まれます。 |
・発見タブ
| ①:投稿に関する情報 | その投稿に対して『いいね』『シェア』『保存』『コメント』をどれくらいの人が行ったか、そしてそれらのアクションがどれだけ早く実行されたかといったシグナルを見て、投稿の人気度を分析します。 発見タブでは、これらのシグナルの重要度が、フィードやストーリーズよりもはるかに高いのが特徴です。 |
| ②:発見タブでのアクティビティ | 『いいね』『シェア』『保存』『コメント』をした投稿や、過去に発見タブの投稿にどういった反応をしたかなどのシグナルを分析ます。 特定タイプの投稿に反応していた場合は、その傾向を分析して似た傾向のコンテンツを多く表示するようになります。 |
| ③:投稿者とのやり取りの履歴 | 関わりを持ったことがある投稿者の場合、その投稿者の投稿に対するおおまかな興味の度合いが分かるようになっています。 |
| ④:投稿者に関する情報 | 直近の数週間で、ほかのユーザーがその投稿者にアクションを実行した回数などのシグナルを分析します。多様な投稿者の中から、より魅力的なコンテンツを見つけるのに役立っています。 |
同じInstagramでも、
フィードと発見タブでおすすめとして
上位に表示されるためのアルゴリズムが異なります。
どちらも興味がありそうなユーザーを
優先して表示されやすいという特徴がありますが、
投稿に対するアクションも重要なポイントとなっています。
3:X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、
Meta社が運営する『Facebook』『Instagram』と違い、
匿名性がより高い特徴があります。
この匿名性の高さから、
『プライベート』『趣味』『ビジネス』など、
活用シーンに合わせてアカウントを分けているユーザーも多くいます。
共通の趣味などでユーザー同士が繋がることも多く、
拡散性が非常に高い特徴があります。
特徴を活かしたフォロー&リポストキャンペーン
などを実施するで、
より効果的に認知を高めることができます。
Xのアルゴリズムとは?
Xの場合、
ユーザーの過去ポストデータを基に、
関心がありそうなポストをランキング化します。
好みやポストの評価など、
色々な角度からのフィルタリングが行われ、
おすすめのポストを表示させる仕組みとなっています。
ポストの順序を決定する指標の一部として、
以下のランキング化のスコアを公開しています。
| ユーザーがポストに対して起こしたアクション | 評価 |
| ①:いいね! | 0.5 |
| ②:お気に入り | 0.5 |
| ③:リポスト | 1.0 |
| ④:返信(リプライ) | 13.5 |
| ⑤:プロフィールを確認してポストにいいね! | 12 |
| ⑥:返信に対してエンゲージメント | 75 |
| ⑦:表示回数を減らす・ミュート・ブロック | −75 |
| ⑧:ポストを報告 | −369 |
『返信(リプライ)』
『プロフィール確認してポストにいいね!』
『返信に対しエンゲージメント』
ユーザーからのこうしたアクションには
特に評価が高いことから、そのポイントが重要視されています。
こうしたポイントを押さえるため、
XではSNSキャンペーンを活用する人が多いのです。
その一方で、
『表示回数を減らす』『ポストを報告』など、
ネガティブなアクションに対しては大幅なマイナスになります。
4:TikTok
TikTokは動画投稿が特徴のSNSです。
動画に特化させることによって、
『アプリ内』だけで動画の撮影・編集・投稿までができます。
TikTokも他のSNS媒体と同様、
独自のアルゴリズムがあり、
ハッシュタグ機能による拡散力が高いのも特徴です。
TikTokといえば少し前まで、
『10~20代の若年層に人気のSNS』
という印象がありました。
ですが、その拡散性や短くて理解しやすい動画投稿
といった仕様がどんどん認知され、
今では利用ユーザーの平均年齢が上がってきています。
2023年時点の調査では、
利用ユーザー平均年齢35.9歳となっています。
TikTokの場合、
フォローしていないユーザーの投稿が、
おすすめとして表示されるという仕組みがあります。
これにより、フォロワーが少ないアカウントでも
投稿直後はユーザーの目に触れやすく、
投稿の戦略によっては認知拡大しやすいSNSと言われています。
TokTokのアルゴリズムとは?
TikTokのアルゴリズムは以下にまとめられます。
| ①:視聴完了時間 | 投稿された動画を最後まで視聴した割合 |
| ②:視聴時間 | 投稿された動画の視聴時間がみられます。 投稿された動画はたくさん再生されてるか、TikTok利用ユーザーが視聴する時間の長い動画は人気があると判断されます。 |
| ③:いいねorコメント | 動画を見たユーザーのアクションが分析されます。 特に「いいね!」と「コメント」が重視される傾向があります。 |
| ④:シェア数 | 投稿された動画が、他のSNSなどにシェアされた数を測定します。 |
| ⑤:再生数(複数回) | 動画の再生数ではなく、ループしたりなど見返された再生回数を測定します。 |
| ⑥:他動画の視聴数 | そのアカウントによって投稿された他の動画の視聴数を測定します。 |
基本的に、TikTokの場合は動画投稿になります。
そのため、動画を最後まで見てもらうこと、
『いいね!』『コメント』『シェア』したくなるかが重要です。
TikTokのアプリ内で撮影・編集・投稿までできるため、
真っ先にユーザーの目に触れる冒頭で、
しっかりと興味を引くタイトルにする等工夫が必要です。
5:LINE
LINEは、他の4つのSNSとは少し異なり、
メッセージアプリとして広く活用されているため、
アルゴリズムではなく利用法や活用法について解説します。
LINEは、
他のSNSよりもユーザーの年齢層が幅広く
あらゆる年代に利用者がおり、
ユーザー数もダントツに多いのが特徴をもっています。
この利用者層の幅広さから、
どのような業種でも利用しやすい特徴もあります。
例えば、自社の公式アカウントを友だち追加してもらい、
定期的に友だち限定の情報提供やクーポンの提供ができます。
友だち登録してくれたユーザーに、
メッセージを配信する「ステップ配信機能」もあり、
プロダクトローンチとしての使い方も可能です。
『自社を認知していて興味がある』とか、
店舗の場合なら『すでに来店したことがある』場合、
お得な情報を個人へ自動配信できるためリピートに繋げられます。
6:まとめ
今回はSNSマーケティングで欠かすことのできない、
SNS媒体ごとの攻略法について解説しました。
SNSごとで媒体の特徴や強みも異なります。
どんな場面でそのSNSを利用するか、
ビジネスシーンで使い分けていくことが
SNSを攻略する時のポイントになります。
狙っているターゲットが使いやすいSNSを運用する、
例えばブランディングのためにTikTokを活用し、
キャンペーン告知のためにXを使うなど
SNSマーケティングでは
どれか一つの媒体を使うだけでなく、
複数のSNS運用によって攻略していくことも重要です。
自社が展開する商品やサービスなど
戦略に応じて使い分けたり、
色々な媒体で展開して新しい年齢層を開拓したりなど、
複数のSNSへの展開は収益アップや
イメージアップへと繋げることができます。
ぜひ、今回の記事をSNSマーケティングに活かしていってください!
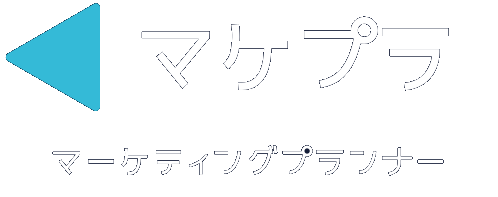





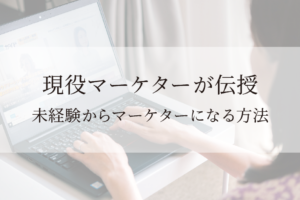
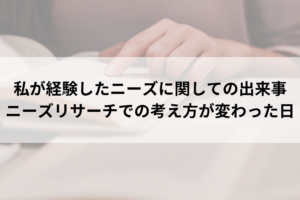

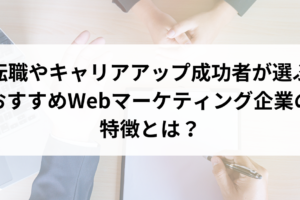

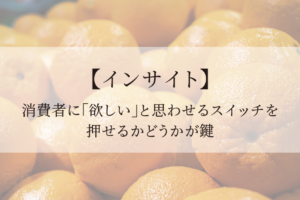
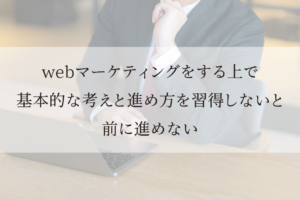

コメントを残す